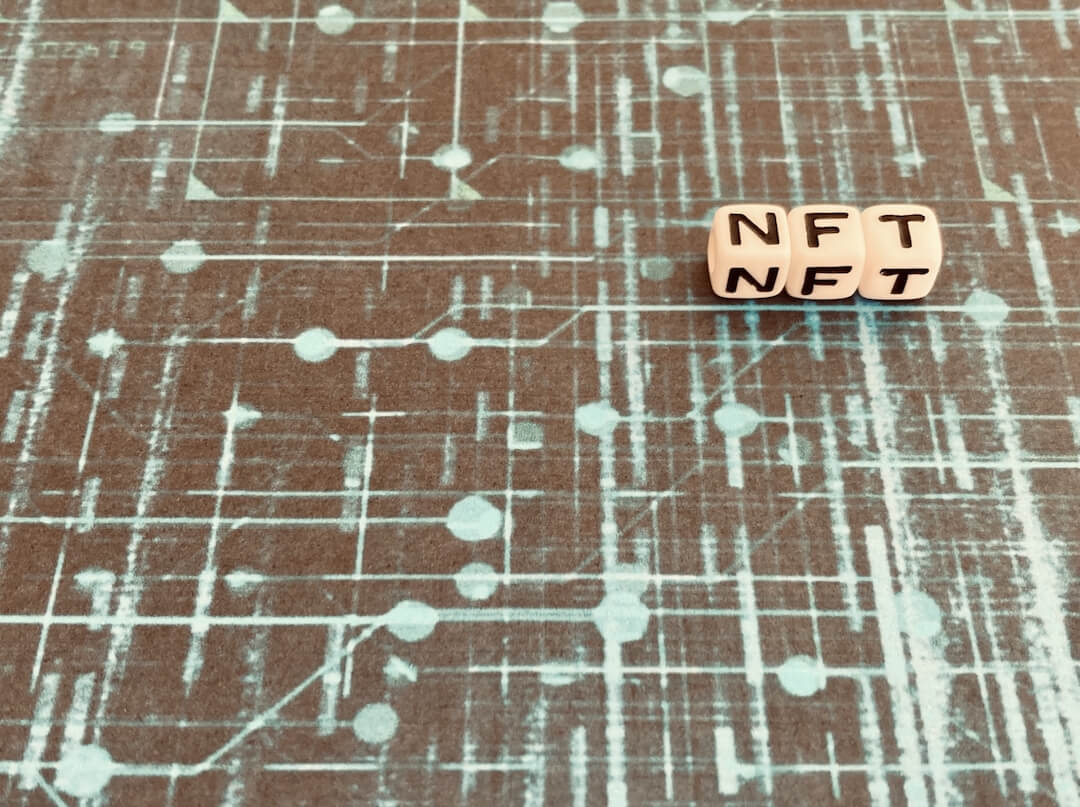【今さら聞けない】仮想通貨の誕生から特徴まで徹底解説
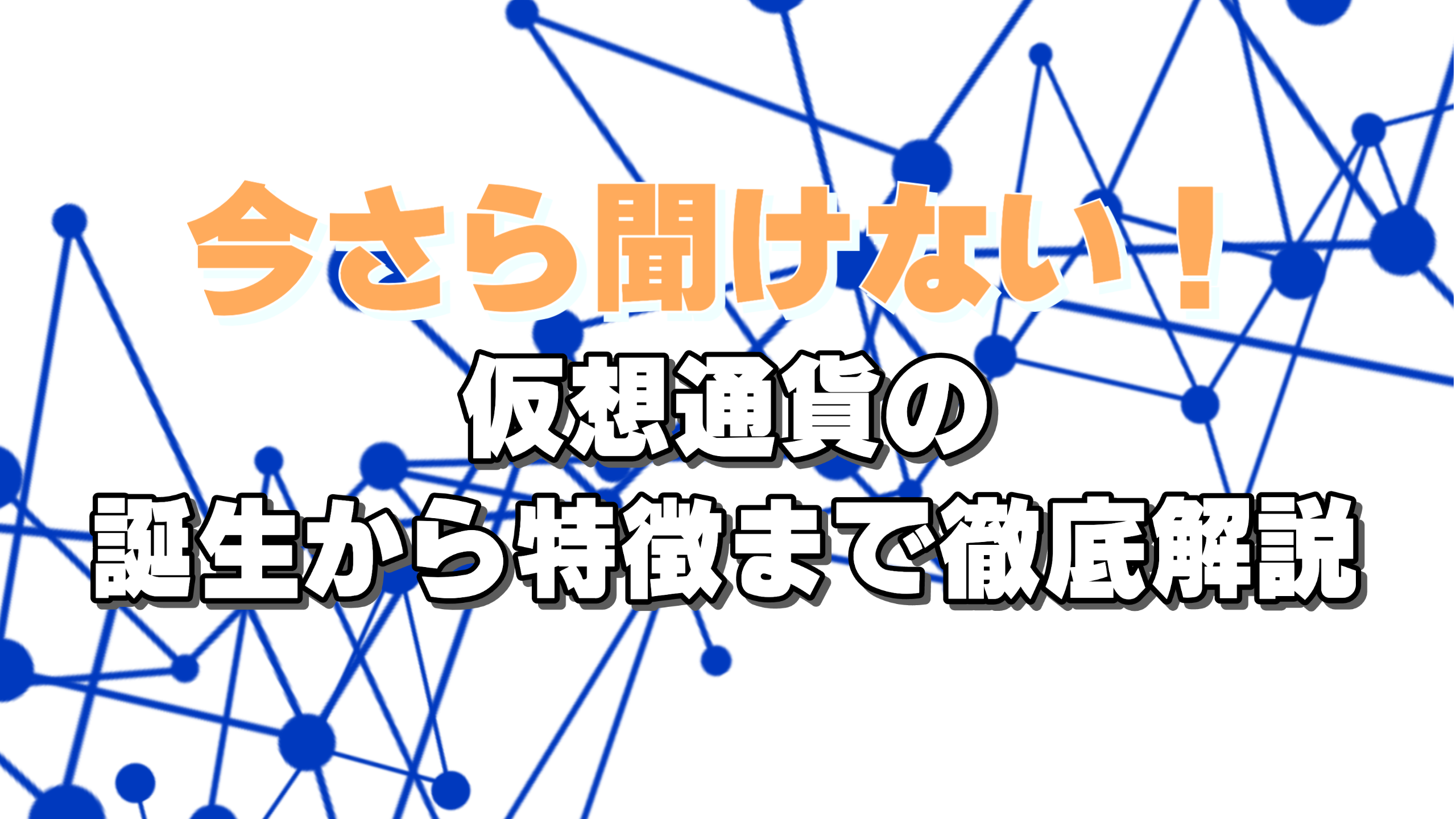
いまや世界中の誰もが一度は聞いたことがある仮想通貨。
みなさんもSNSやニュース、TVなどで聞いたことがある方がほとんどだと思います。
そこで、
「仮想通貨を始めたいけど、よくわかんないから何か怖いな」
「なぜこんなに仮想通貨が流行っているの?」
そんな方に向けて仮想通貨の誕生からその背景、特徴や仕組みを徹底的に解説します。
仮想通貨(暗号資産)という名前・呼び方
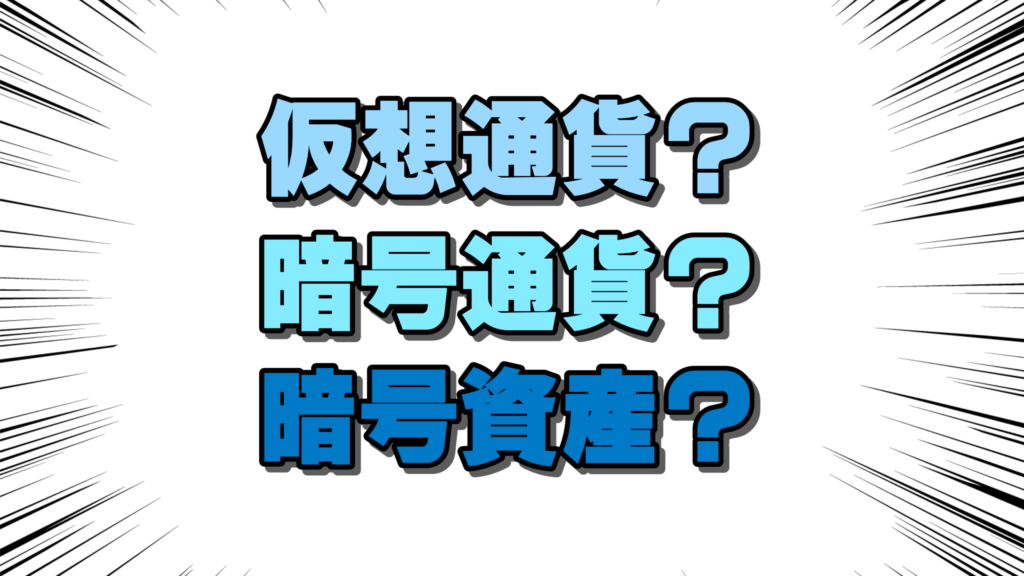
仮想通貨の解説に入る前に、名前・呼び方について解説します。
海外では一般的に英語で
「Crypto Currency(クリプトカレンシー)」と呼ばれています。
「Crypto=暗号」「Currency=通貨」で日本語で言うと「暗号通貨」となります。
2014〜2015年ごろ、日本でビットコインが広く知られ始めた際に関係者たちの中で、
「ビットコインは、法定通貨(Fiat Currency)ではなく、
仮想通貨(Virtual Currency)である」
という認識で呼んでいたことからTVやニュースでも「仮想通貨」として発信したとされています。このことから、日本では「仮想通貨」という名前・呼び方が広く定着しました。
しかし、この「仮想通貨」という呼び方では様々な誤解を生んでしまうのでは?ということで金融庁が検討を行い、2020年5月1日から「改正資金決済法」の施行に伴って、資産としての意味合いが大きいということで「暗号資産」に統一されました。そのため現在では、正式には(行政上の手続き等)「暗号資産」として呼ぶ必要があります。
ですが、この記事ではみなさんが理解しやすいように、私たちが普段から聞き慣れている「仮想通貨」として解説していきます!
仮想通貨(暗号資産)とは
![]()
仮想通貨とは(暗号資産)とは、ネットワーク上で利用できる暗号化された通貨のこと。
ブロックチェーン技術や複数の暗号技術で作られています。
ネットワーク上にだけ存在するので、私たちが普段使っている紙幣や硬貨と違って目には見えませんが、ドルや円などの法定通貨と違って、世界共通の同じ価値で利用できます。
ドルや円などの法定通貨は、その国が法的に価値を保証して流通量などを管理していますが、対して仮想通貨はそういった価値を保証するものはありません。
ではなぜ、このような特徴を持つ仮想通貨が生まれたのが、そしてここまで広まったのかについて次章から詳しく解説していきます。
仮想通貨(暗号資産)はどのように生まれた?

2008年に、「サトシナカモト」という正体不明の人物が一つの論文を公開しました。
その論文の内容は大きく2つ
- 金融機関を通さない、暗号通貨という新しい概念
- そのシステムの土台となるブロックチェーン技術について
この論文に興味を持った複数のエンジニアたちが有志で開発を進め、
論文公開の翌年2009年に世界初の仮想通貨(暗号資産)ビットコインが誕生しました。
論文が公開され、開発からビットコインが誕生したきっかけとして、2008年9月に起きた金融危機「リーマン・ショック」が一番大きな要因とされています。
アメリカ超巨大大手の投資銀行だった「リーマンブラザーズ」が経営破綻したことで、世界的に株価が下落、他の大手金融機関が連なって経営危機を引き起こしました。これにより、世界のお金の流れがストップしてしまい、世界的に不景気となり大混乱が起きました。
あまり社会情勢に詳しくない方でも「リーマン・ショック」という言葉は聞いたことがある方も多いのではないでしょうか?
この世界中で大混乱となった「リーマン・ショック」が引き起こした大手金融機関や景気改善策として、アメリカ政府が米ドル紙幣を大量に発行したこと等が、一部の人から不信感が募らせました。
「法定通貨を中央銀行が管理して本当に大丈夫なの?」
「通貨の価値を一方的に決めさせて大丈夫なの?」
といったように問題視する声があがっていました。
こういった背景があり、金融機関などの中央集権的な管理者を必要としない仮想通貨(暗号資産)ビットコインの開発が進み、誕生したとされています。
元となった論文を公開した「サトシ・ナカモト」ですが、正体は今だに分かっておらず、日本人なのか、人物でなく団体や組織なのか等、様々な説が世界中で流れていますが、依然として謎に包まれたままとなっています。
仮想通貨(暗号資産)が注目されている理由

現在は、投資・投機目的がほとんど
仮想通貨がなぜここまで注目されているのか。それは
「世界で起きている様々な問題を解決できる
仮想通貨にはその価値がある」と信じられてきているから。
しかし、私たちが普段使っている法定通貨と比べるとまだまだ普及しておらず、画期的で新しいものだからこそ多くの人が投資や投機目的で取引をしています。
仮想通貨の多くは、価値を保証する国などの管理者がいないため、売買取引によって値動きが激しく行われており、稼ぐ目的で注目されているのが実情です。
仮想通貨が目指す世界
仮想通貨・ブロックチェーン誕生のきっかけとなった「サトシ・ナカモト」は、
- 誰も介入できない
- 決してダウンしない
- 公正に取引を記録できる
- 政府等の管理者に縛られない
こういったシステム・サービスを作るためにビットコインを生み出したと言われています。
その背景には、政府や行政、企業などで公的な情報の紛失や書き換えなどの、
悪意ある不正な事件が国内外問わず、世界中で多発している問題があります。
また、世界では様々な理由で「銀行口座を持たない人」が発展途上国を中心に約17億人いるとされていますが、そのうち3分の2の人々は携帯(スマホ)を持っています。
海外送金の例で言うと、出稼ぎ等で自国の家族へ向けた仕送りができなかったり、できたとしても銀行の高い手数料コストや多くの時間がかかってしまうなどの問題で困っている人々が多くいるのです。
このように、世界で様々な問題を抱えている中、こういった問題を解決できる技術に世界中のエンジニアが注目し、ビットコイン開発までに至ったとされています。
徐々に普及へ
インターネット上での新しい通貨・技術ということで、実際に使う機会がなかったり、誰もが使いやすいサービス、知識がない人でも使えるような準備が進んでいない状況でから、日本でも仮想通貨を保有したり取引している人の割合はまだまだ少ないです。
ですが、2021年エストニアがビットコインを正式に法定通貨として採用したり、ここ数年で数々の大手企業がビットコイン決済を採用したりと、徐々に普及が進んでいる状況です。
ではなぜ、仮想通貨が多くの人の生活を変えていくと期待されているのか、注目されているのかについて、仮想通貨の特徴や仕組みをもとに次章から解説します。
仮想通貨(暗号資産)の特徴・仕組み

仮想通貨の特徴
仮想通貨の特徴は大きく4つ
- 中央管理者を必要としない
- 発行上限枚数がある
- 世界の法定通貨と換金可能で、送金が高速かつ低コスト
- 機能の改善が可能・アプリケーション開発にも使われる
中央管理者を必要としない
私たちが普段使っている法定通貨では、国や中央銀行などが中央で通貨の価値の保証や管理を行なっていますが、仮想通貨の多くはそういった管理者がいません。
仮想通貨のネットワークに参加している全員で管理しあうシステムになっているため、中央にいる団体や組織などの管理者が一方的に操作をすることができないようになっています。
発行上限枚数がある
私たちが普段使っている法定通貨や紙幣は、中央銀行が経済の状況に合わせて流通量を増減させて通貨の価値を調節しています。
例えばビットコインでは、発行上限を2,100万枚とあらかじめプログラムされています。
世界の法定通貨と換金可能で、送金が高速かつ低コスト
ドルや円などの法定通貨と換金が可能で、換金せずとも仮想通貨を送金や決済に使うことができます。銀行で海外に送金する際、高い手数料と時間がかかってしまいますが、仮想通貨の場合、圧倒的に低い手数料、ものの数分で送金ができます。
機能の改善が可能・アプリケーション開発にも使われる
そもそも仮想通貨はインターネット技術のひとつなので、機能向上のための改善が可能です。また、送金や決済だけではなく、自動で契約取引を行うことができる「スマートコントラクト」と呼ばれる機能が搭載された仮想通貨(イーサリアム等)も存在していたりと、様々な目的のために作られた多種多様な仮想通貨が生まれています。
なので今後さらに開発が進み、より簡単に、便利になっていく可能性を秘めています。
仮想通貨を支える技術
法定通貨にはない様々な特徴をもつ仮想通貨ですが、主にブロックチェーンという技術が使われていることによって仮想通貨の特徴を実現可能にしています。
ブロックチェーンの特徴を簡潔にまとめると以下の3つ。
- 管理者のいない非中央集権システムが実現可能
- 改ざん不可能な暗号技術
- 信頼性の高いユーザー間取引
このブロックチェーンの、改ざんできない暗号化された状態で情報が記録され、取引の記録をユーザー同士で安全に管理できる技術が、仮想通貨との相性がとてもマッチしているのです。
くわしくはこちらの記事で解説していますので是非読んでみてください。
仮想通貨の種類

仮想通貨は、大きく「ビットコイン」と「アルトコイン」に分類されます。
※アルトコイン=ビットコイン以外の仮想通貨の総称
アルトコインの中で知名度も取引量も少ない仮想通貨は「草コイン」とよばれていますが、この草コインを含めた全ての仮想通貨の種類は現在なんと「約15,000種類」もあります。
※2022年1月現在。上場していない仮想通貨含む。
仮想通貨は自身でプログラミングさえできれば個人でも発行できるため、様々な目的をもった仮想通貨が生まれ続けています。
そのため、中には詐欺まがいの仮想通貨も存在しているため実際に売買する際には、本当に信頼できるのか、将来性があるのか等、慎重に選ぶ必要があります。
仮想通貨(暗号資産)のメリット、デメリット

ここまで仮想通貨にどんな特徴や仕組みがあるのかについて解説しました。そこで、実際に仮想通貨を購入したり投資することによるメリットとデメリットは何なのか?という点を解説します。
メリット
- 大きく稼げる可能性がある
- 24時間365日リアルタイムで取引可能
- 少額から取引可能
大きく稼げる可能性がある
仮想通貨は価格変動(ボラティリティ)が大きいので、株式や投資信託などに比べると比較的利益が出やすいです。
とても価格が低かった仮想通貨が、著名な投資家や大企業の発言などにより注目が集まり、急激に価格が上昇することがここ数年の間に何度も起きています。
24時間365日リアルタイムで取引可能
株式投資の場合、証券取引所の取引時間内(平日9〜15時)でなければ取引ができません。
対して仮想通貨は、ネットにさえ繋がっていればいつでも取引可能です。
少額から取引可能
ほどんどの仮想通貨取引所では、「1,000円以下」から購入できます。
株式やFX、その他の投資商品と比べると桁違いに低価格から取引ができるので、気軽に始められます。
デメリット
- 価格の変動が激しく安定しない
- 取引所のハッキングやセキュリティ管理のリスク
- 最新情報などは英語が多い
価格の変動が激しく安定しない
メリットと反対ですが、価格変動(ボラティリティ)が大きい分、短期間で価格が下がることがあります。大きな損失をしてしまう可能性や、価格変動の動きを読むのが難しいことがあります。
取引所のハッキングやセキュリティ管理のリスク
仮想通貨は暗号化されたセキュリティ抜群の通貨ではありますが、それを取り扱う取引所へのハッキングによって仮想通貨が流失する事件が過去に起きています。
また、仮想通貨はウォレットという財布のようなもので管理しますが、これにアクセスするためのパスワードを紛失してしまったり、漏洩するリスクがあります。そのため、自身でしっかり管理する必要があります。
最新情報などは英語が多い
仮想通貨に限らず、投資などを始めると今後の動向を読み解くために、日頃から情報収集をするようになるかと思います。しかし、仮想通貨を使った取引や開発などは、日本国内に比べると圧倒的に海外の方がさかんに行われています。そのため、最新情報を追いかけようとすると、英語での情報が多くなるため、あまり英語がわからない方はとっつきにくいかもしれません。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
仮想通貨(暗号資産)自体そのものは知っている方が多い中、仮想通貨が生まれた経緯や背景まで理解されている方はあまり多くなかったのではないでしょうか。
世界の様々な問題を解決するために生まれた仮想通貨ですが、少しづつですが日々普及が進んでいます。しかし、現在はやはり投資や投機目的で興味を持っている方がほとんどだと思います。
これから仮想通貨取引を始めたい方は、仮想通貨が取引所で売買ができるようになることを上場と言いますが、日本国内で上場していて売買ができる仮想通貨は、日本が厳正な審査をもとに選定したものとなっているので、まずはその中から選んでいくと良いでしょう。
皆さんの、今後の仮想通貨の動向を読み解くヒントになれば幸いです。